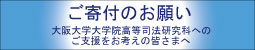研究科長室より
CBT元年
2025/03/28
法科大学院界隈では、CBT化をめぐる議論が活発化しています。今さらながらの話ですが、CBTとはComputer Based Testingのことであり、雑ぱくに言ってしまうと、パソコン(PC)を使って答案を作成し、答案をデジタルデータとして扱う試験方法のことを意味します。法科大学院界隈でこのCBTが話題になっているのは、言うまでもなく、令和8(2026)年度から司法試験がCBT方式によって実施されることが決まったためです。つまり、今から1年3ヶ月ほど先の令和8年7月に実施予定の司法試験は、PC(モニターサイズが16インチのWindows11のPC)で答案を作成する試験方式になるということです。
以前から弁護士会の一部で、司法試験CBT化を推奨する声がありました。諸外国でも司法試験のCBT化が進んでおり、お隣の韓国でも昨年から論文式試験でCBT方式が導入されています。こうした潮流に沿うかのように、政府も、昨年6月21日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の中で、「司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化」を明記した上で、令和8年度にはCBT方式による試験を実施する旨を宣言しました。その意味で、司法試験のCBT化は国策といってもよい様相を呈しています。
そもそも文書を手書きで作成するよう求められる実務上の機会はほとんどありません。手書きの方が便利な場面はもちろん存在しますが、少なくとも法律答案の作成は、そのような場面ではありません。そう考えると、司法試験CBT化は(遅ればせながらも)ようやく来るべきものが来たということなのかもしれません。答案を採点する側の立場からしても、ようやく読めない文字と格闘しなければならない苦痛から解放されるという気持ちが湧き上がってきます。CBT化のメリットが大きいことは明らかです。しかし、このことはCBT化に課題がないということを意味しません。
現場感覚として司法試験CBT化は急に決まった感がある上、司法試験で使われるアプリケーション・ソフトが公開されたのも先月末であり、これを試行錯誤しながら1年ほどかけて手直ししていくことになっているなど、実施のスケジュールが窮屈です。司法試験の問題用紙や下書き用紙も画面上で扱うとのことですが、これはむしろ紙の方が便宜ではないかとの声があるのに、受験生からの訴えが少ないせいか(まだ情報が行き渡っていないのかもしれません)、当局には姿勢を改める気配がありません。医歯薬系の国家試験では、既にCBT方式が用いられているとのことですが、短答式試験のみならず、論文式試験もCBT化するのは、これが初めての経験になると思われるにもかかわらず、全体的に余裕がないのです。
先日、本研究科でもプレテストを実施しました。しかし集合方式のプレテストには僅かの人しか集まらず、個別方式のそれに参加した人を入れても受験生数が少なかったことを考えると、学生はまだピンと来ていないのではないかと思わせられました。おそらく今年7月の司法試験(手書き方式の最後の試験)が終わるまでは、CBT化対応に積極的になれないのでしょう。他方、CBT方式の受験では、自分の手持ちのPCが使用できるわけではなく、アプリケーションも普段使うことのない特殊なものなので(予測変換機能などはない)、受験時までにある程度慣れておかないと、使い勝手の悪さばかりが気になることになりかねません。手書きのときの方が実力発揮できたというのでは意味がないのです。
司法試験CBT化は法科大学院のあり方にも波及しています。今やすべての法科大学院が期末試験のCBT化も視野に入れています。期末試験をCBT化するとなると、試験時における不正対策や技術的トラブル対策が、法科大学院の責任になります。しかし、法科大学院に論文式試験のCBTシステムを開発する能力はないので、自ずと外部からシステムを購入するほかなく、そのための財政負担をどのようにして賄うかという問題と直面することになります。さらには電源等の増設やネットワーク環境の整備など、解決すべき課題は枚挙にいとまがありません。これもお金の問題に直結します。
泣き言のような文章になってきたので、ここで締めくくることにしますが、今年は法科大学院にとって「CBT元年」になるということをお伝えしたかったということです。私にとって次の1年は科長業務の最終年になります。数多くの課題を自覚しつつ、対応に当たりたいと思っています。