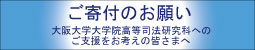研究科長室より
エートスと使命感を育む法科大学院へ
2025/05/23
この場を借りて、本研究科の在校生に研究科長としてのメッセージを送りたいと思い、毎回、せっせと執筆しているのですが、力を込めて書いていると、どうにもお説教じみてくるし、筆を抑えて書いていると、なぜか独り言のような調子になってしまうなど、なかなかうまくいきません。それにメッセージの中身が似たり寄ったりになってしまい、新鮮みがなくなってきたような気もします。煮詰まってきたという感じでしょうか。こういうときは開き直るに限ると割り切り、いつもの話になってしまうと分かる場合でも、あえて躊躇せず、堂々と主張することに努めるべきだと思いました。今回はそういう話です。
まず、法科大学院とはどういうところかという点から確認しておきます。今さらですが、法科大学院は法曹養成に特化した専門職大学院です。法曹養成という法科大学院の目的を達成するため、本研究科は「新時代を担う、真のLegal Professionalsの育成」を基本方針として掲げ、これを実現するための方法を日夜模索しています。真のLegal Professionalsを育成するためには、もちろん、それに見合う教育プログラムを設け、そのプログラムを実施に移す有能なスタッフを配置し、施設等の物的設備を整えなければなりません。そのためには財源の確保も必要になります。
こうした外的条件の整備は確かに不可欠ですが、外的条件の充実に尽力するだけでは、なお真のLegal Professionalsの育成には足りないのではないかと思っておりました。私が思うに、法曹には、法律家共同体を支えるエートスと、公共に奉仕しようとする使命感が求められます。それゆえ、法科大学院は単に法的知見を供給するだけでなく(もっといえば受験勉強を促すだけでなく)、法曹が備えるべきエートス(Ethos)や使命感も体得できるよう配慮しなければなりません。とはいえ、エートスや使命感なるものは、いうまでもなく、教師が教壇から説いてどうにかなるものではありません。一人一人の法曹がそれを内面化してくれなければ、ただのお題目に終わってしまいます。
本研究科に入学した学生のほとんどは、いちいち指示されなくても、試験のための勉強はやってくれます。個々の勉強の仕方に巧拙があるとしても、それをやろうという気持ちさえ保たれているのなら、改善の余地はあります。しかしエートスや使命感の体得となると、期末試験とも司法試験とも関係がないだけに、元々それを体得して入学してきた学生を別にすると、法律家のエートスも使命感もないまま、修了後法曹資格を得ただけということになりかねません。それでは真のLegal Professionalsになったといえないでしょう。法曹にとって、法律の知識は必要条件ではあっても、十分条件ではないというべきだからです。
法律の知識以外に、法曹が内面化すべきエートスや使命感をどのようにして体得すればよいのか。残念ながら、この問いに一言で答えることはできそうにありません。そもそもエートスや使命感とは、経験を積み重ねながら体得していくような性格のもので、教師が頭ごなしに押しつけても、反発を感じるだけで、身体に馴染まないと思われるからです。かといって、自習室や勉強部屋で一人黙々と学修しているだけでも身に付かないでしょう。それはおそらく法律家共同体の中で相互にコミュニケーションをとりながら、自分の考えと他人の考えを摺り合わせていこうとする過程で体得されていくものではないでしょうか。
そうであれば、法科大学院においても、このような体験が可能になる場を提供することに努めるべきということになりましょう。法律家共同体の範囲を広く捉えれば、学生同士の議論の場もそこに該当しますし、学生委員会のような学生自治組織もその役割を果たしてくれると思います。さらにエクスターンシップやインターンシップの場も、法律家共同体との接点です。本研究科を修了して活躍している法曹たちも、ロールモデルになると同時に、法曹のエートスや使命感を教えてくれる存在として、貴重な役割を担っています。本研究科でも、こうしたコミュニケーションの機会を少しでも多く提供できるよう、企画を構想していくつもりです。